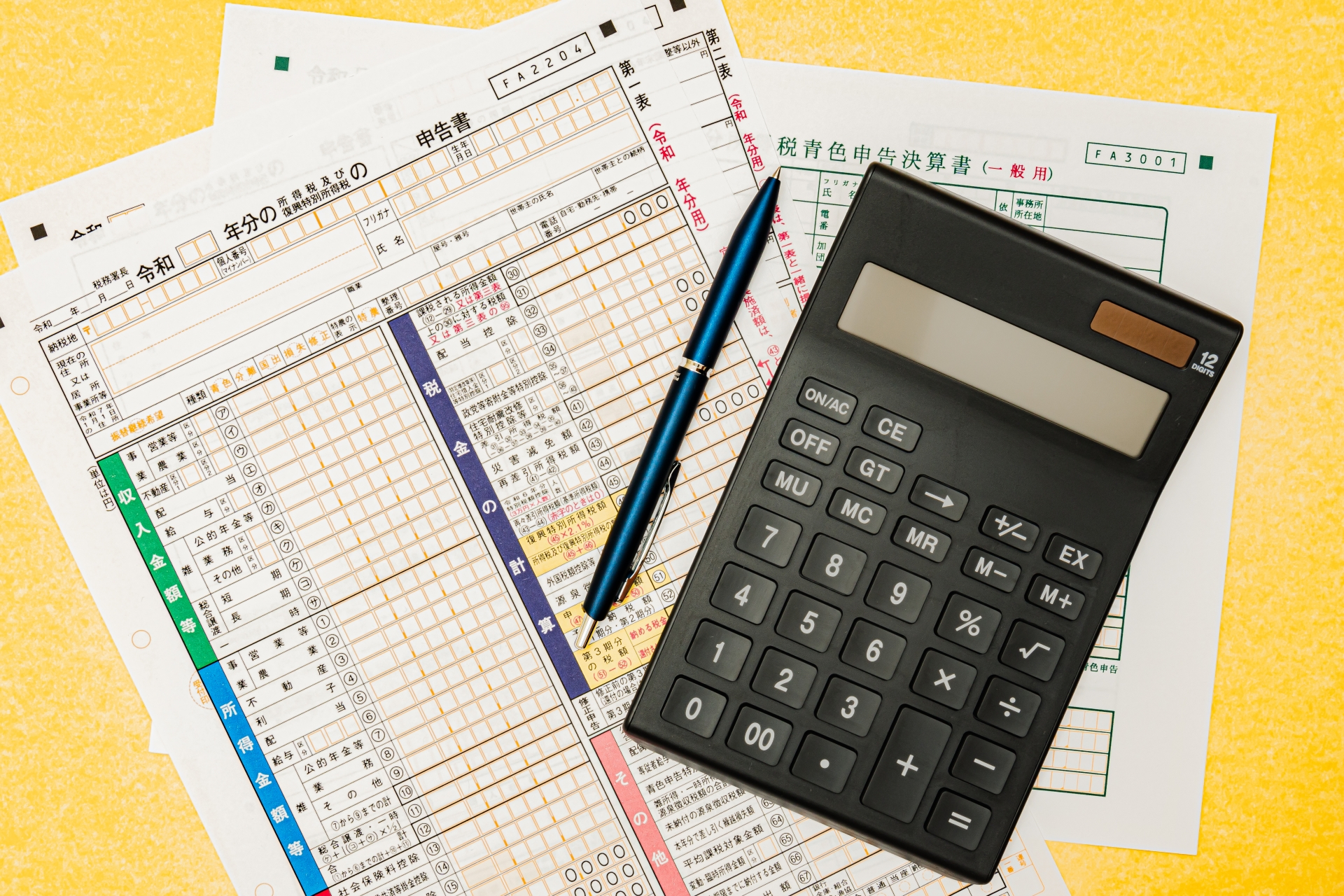
(※イメージ画像)
個人事業主として活動を始めると、避けて通れないのが確定申告です。
「いくらから確定申告が必要なの?」という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、確定申告が必要になる所得の基準額や、その計算方法について分かりやすく解説します。
また、節税に役立つ基礎控除や経費の考え方、申告を怠った場合のペナルティについても触れていきます。
確定申告の基本を押さえ、安心して事業を継続するための知識を身につけましょう。
確定申告が必要になる所得の基準額とは?
個人事業主が確定申告をしなければならない基準は、所得の金額によって決まります。
所得とは、売上(収入)から経費を差し引いた金額のことです。
- 所得 > 48万円
この「48万円」という金額は、基礎控除と呼ばれる所得控除の金額です。
所得控除とは、税金を計算する際に所得から差し引くことができるもので、基礎控除は誰でも一律に受けることができます。
つまり、売上から経費を差し引いた所得が48万円を超えた場合、確定申告をして納税する必要がある、ということになります。
注意点:
- 収入と所得の違い: 収入(売上)が100万円あったとしても、経費が60万円かかっていれば、所得は40万円となり、確定申告の義務はありません(ただし、所得税の還付を受けるためや、住民税の申告のために確定申告をした方が良い場合もあります)。
- 事業所得以外の所得: 給与所得や不動産所得など、事業所得以外に所得がある場合は、それらを合算して判断する必要があります。
- 赤字の場合: 所得がマイナス(赤字)になった場合でも、青色申告をしている場合は、その赤字を翌年以降に繰り越すことができるため、確定申告をすることにメリットがあります。
所得48万円以下でも確定申告をするメリット
「所得が48万円以下だから確定申告は必要ない」と考える方もいますが、実は確定申告をすることで得られるメリットも多くあります。
- 源泉徴収された所得税の還付: 取引先から報酬を受け取る際、事前に所得税が源泉徴収されている場合があります。
所得が48万円以下であれば、本来所得税はかからないため、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が全額還付されます。 - 住民税の申告: 所得税の確定申告は所得が48万円以下だと不要ですが、住民税の申告は市区町村への届け出が必要です。
確定申告をすれば、その情報が市区町村に自動的に連携されるため、別途住民税の申告をする手間が省けます。 - 国民健康保険料の軽減措置: 国民健康保険料は、所得に応じて金額が変わります。
確定申告をして所得を正確に届け出ることで、所得が低い場合に保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。 - 青色申告の赤字繰り越し: 青色申告承認申請書を提出している個人事業主は、事業で赤字が出た場合、その赤字を最大3年間繰り越すことができます。
翌年以降に利益が出た際に、繰り越した赤字と相殺することで、節税効果を得られます。
これらのメリットを考慮すると、所得が48万円以下であっても、確定申告を行うことを検討する価値は十分にあります。
確定申告の計算方法:所得と経費の考え方
確定申告の計算は、以下のシンプルな式で成り立っています。
- 所得 = 売上(収入)- 経費
この計算を正確に行うためには、「経費」の考え方を正しく理解することが重要です。
経費として認められるもの: 経費として認められるのは、事業を行う上で直接必要になった費用です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 事務所家賃や水道光熱費: 事業で利用している部分の費用
- 通信費: 携帯電話やインターネットの料金
- 旅費交通費: 取引先への移動費用
- 消耗品費: 文房具やプリンターのインクなど
- 外注費: Webサイト制作やロゴデザインなどを外部に依頼した費用
- 接待交際費: 取引先との飲食費用
家事按分: 自宅を事務所として使っている場合や、プライベートでも使用する携帯電話を仕事でも使う場合、その費用を事業で使った分だけ経費として計上することができます。
これを家事按分と言います。
合理的な基準(使用時間や面積など)に基づいて按分し、帳簿に記載することが大切です。
日々の領収書やレシートをきちんと保管し、どの費用が事業に必要なものだったのかを明確にしておくことが、確定申告をスムーズに進めるための第一歩です。

(※イメージ画像)
確定申告をしないとどうなる?ペナルティについて
確定申告の義務があるにもかかわらず、申告を怠った場合や、申告内容に不備があった場合は、さまざまなペナルティが課せられます。
- 無申告加算税: 期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。
納税額に対して、原則として15~20%の割合で加算されます。 - 延滞税: 納税が遅れた場合に課せられる税金です。
法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、年率で加算されます。 - 重加算税: 意図的に所得を隠したり、不正な方法で税金を逃れようとした場合に課せられる非常に重いペナルティです。
無申告加算税や過少申告加算税の代わりに、35~40%の割合で課せられます。
これらのペナルティは、本来支払うべき税金に加えて課せられるため、大きな負担となります。
また、悪質な場合は追徴課税の対象となり、社会的な信用を失うことにもつながりかねません。
期限内に正確な申告を行うことが、安心して事業を続けるための基本です。
確定申告を効率的に行うためのツールと方法
確定申告は複雑な手続きに感じるかもしれませんが、最近ではさまざまなツールやサービスを利用して効率的に行うことができます。
- 会計ソフトの活用: クラウド会計ソフトを利用すれば、日々の取引入力から確定申告書の作成までを自動化できます。
銀行口座やクレジットカードと連携させることで、取引明細を自動で取り込み、仕訳を自動で作成してくれる機能もあります。
これにより、手作業での入力ミスを減らし、時間を大幅に節約できます。 - e-Taxでの電子申告: e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネットを通じて自宅から確定申告ができます。
e-Taxで申告すると、青色申告特別控除が最大65万円になるなど、電子申告ならではのメリットもあります。 - 税理士への相談: 事業規模が大きくなってきた場合や、複雑な税務処理が必要な場合は、税理士に相談するのも良い方法です。
専門家のアドバイスを受けることで、節税対策をより効果的に行ったり、申告の手間を省いたりすることができます。
確定申告は、個人事業主としての義務であると同時に、自身の事業の経営状況を把握する良い機会でもあります。
便利なツールを賢く活用し、正確かつ効率的に確定申告を行いましょう。


コメント